検索ワード
研究プロジェクト
 |
Summary | 高齢社会の到来とともに、医療(介護・福祉含む)の重要性はますます高まっていますが、一方でその提供にかかるコストも高まっています。そのため、質が高く効率的な医療の提供が求められています。その際、患者・利用者に直接実際に医療提供しているのは医療機関ですので、費用対効果の高い医療提供の実現には、医療機関の経営管理が極めて重要です。日本の医療機関の中心を担う医療法人を中心とした医療機関の経営に関する研究を通じて、今日の課題に対する解決策を模索していきます。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | 荒井耕、渡邊亮、阪口博政、古井健太郎、石田円、田村桂一 |
 |
Summary | 本研究は、中高年の健康増進や社会的厚生向上のための政策的含意を得ることを目的とする。分析に際しては、所得や学歴、就業形態など様々な個人レベルの社会経済的要因だけでなく、居住地域の格差・貧困状況、社会参加活動の度合いや就業状況など地域レベルの社会経済的要因にも注目し、中高年の健康の社会的決定要因を動学的な枠組みの下で分析するとともに、政策シミュレーションとして、年金・雇用制度改革が健康格差に及ぼす影響を試算する。さらに、中国で実施されている各種大規模社会調査の個票データも活用して日中比較を試みる。 |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 基盤研究(C) 23K01419 | HIAS team members | 小塩隆士 |
 |
Summary | 労働者の健康状況は本人の幸福度に影響するばかりでなく、医療費や労働生産性を通して企業や社会全体に大きな影響を与える。本研究では、ある企業から提供された、健康診断・ストレスチェック・労務の個票データを用いて、勤務状況に影響する身体的及びメンタル・ヘルスに関する健康要因の分析を行う。本研究は、労働者の健康状況の改善のみならず、医療費の削減や生産性の向上につながり、社会的にも大きな意義がある。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | 縄田和満 |
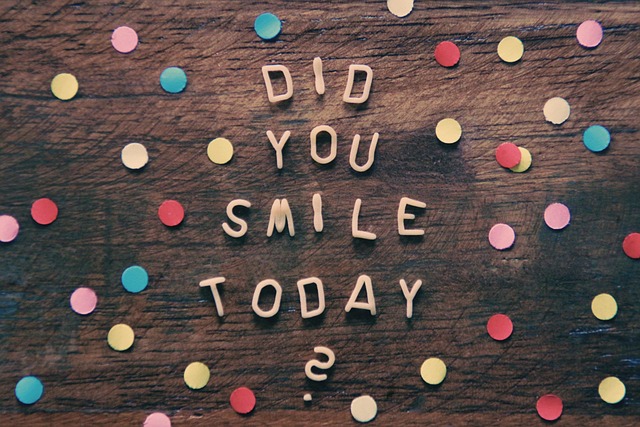 |
Summary | コロナ禍で進行した「災害級」とも呼ぶべき少子化や子どもを取り巻く環境の悪化に対して、①少子化を止める可能性のある施策の本格的な評価、②長引くコロナ禍でどのような子どもや若者が不利益を被っているのか、という2点を明らかにするべきだと考えるようになった。そこで、①については不妊治療に対する助成の効果、出産一時金の効果を検討することとした。②については個票データを用いた様々な解析を予定している。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | 高久玲音 |
 |
Summary | Housing is a largely overlooked social determinant of health, and its impact on long-term care is even less understood. This study is the first to investigate the relationship between housing and long-term care in Japan, addressing two key questions: To what extent, and in what ways, are housing deficits associated with long-term care needs and utilisation among older Japanese adults? And if these deficits were addressed, how much could be saved in public long-term care insurance expenditures? Using nationally representative longitudinal data, this study estimates potential cost savings and assesses the policy implications. The findings will contribute to emerging international discussions and provide valuable insights for integrating housing considerations into long-term care and public health strategies, promoting cross-sectoral collaboration and guiding more effective resource allocation. Project [2025-04-01-2028-3-31] ※日本語訳準備中 |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 若手研究 25K16662 | HIAS team members | Ruru Ping |
 |
Summary | It is now well known that infection with COVID-19 has long-term impact on health, and that it may increase death and illness from a wide range of causes. This project will use data from the Ministry of Health and the Japan Statistics Bureau to assess the impact of the COVID-19 pandemic on population health in Japan. It will use sophisticated intervention analysis techniques developed by the principal investigator for assessing the impact of sudden events on population health, to comprehensively assess the effect of the COVID-19 pandemic on the health of the Japanese people. |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 基盤研究(B) 24K02676 | HIAS team members | Phuong The Nguyen (Co-I) |
 |
Summary | It is now well known that infection with COVID-19 has long-term impact on health, and that it may increase death and illness from a wide range of causes. This project will use data from the Ministry of Health and the Japan Statistics Bureau to assess the impact of the COVID-19 pandemic on population health in Japan. It will use sophisticated intervention analysis techniques developed by the principal investigator for assessing the impact of sudden events on population health, to comprehensively assess the effect of the COVID-19 pandemic on the health of the Japanese people. |
|---|---|---|
| Daiwa Securities Foundation | HIAS team members | Phuong The Nguyen (PI) |
 |
Summary | Colorectal cancer (CRC) incidence is increasing among adults under 40 years old in Japan, highlighting gaps in current screening due to inadequate understanding of age-specific risk factors. In this study, we use a novel data linkage framework that integrates statistical surveys, cancer registries, and environmental data to identify major CRC risk factors in young adults. Advanced statistical and machine learning models are used to analyze dietary, lifestyle, and environmental factors. Obtained findings can guide targeted prevention, enhanced screening guidelines, and public health policies to address the increasing incidence of CRC among young adults in Japan. |
|---|---|---|
| Hirose Foundation | HIAS team members | Phuong The Nguyen (PI) |
 |
Summary | Lung cancer in never smokers (LCINS) is an emerging public health challenge in Japan and globally. Current prevention efforts face significant knowledge gaps, particularly regarding gender- and histology-specific risk factors, partly due to fragmented data sources. This project addresses these gaps by developing an innovative data integration approach, employing advanced analytical techniques to explore LCINS risk factors comprehensively. The results will provide critical insights to support future strategies for lung cancer prevention, screening, and policy improvements in Japan. |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 若手研究 25K20503 | HIAS team members | Phuong The Nguyen (PI) |
 |
Summary | ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)は、持続可能な開発目標のゴール3でも掲げられ、国際社会の重要政策課題である。UHCは、資源プールと再配分を通して人々を高額な医療費の自己負担から保護し、医療機関への支払い機能を活用し、保健医療サービスの効率性と質を図る制度を推奨している。 本研究は、国際政策レビューにより、国際社会でのUHCの概念の変遷と新しい要素を同定し、我が国が行うべき施策を纏める。また、コロナ禍を経て健康危機の政策対応に関する国際議論が高まる中、UHCの視点から概念を整理し、低中所得国で平時から健康危機に備えておくべき保健システムの要件を、文献レビューとステークホルダーの経験を基に纏める。更に、近年、UHCの礎石として効果的で安全なサービスの重要性が指摘されており、UHCの議論における支払い機能を活用したサービスの質の向上に関し、概念とエビデンスを整理し、低中所得国に有用な政策提言を纏める。 |
|---|---|---|
| 厚生労働科学研究費:24BA1002 | HIAS team members | 本田文子、Ruru Ping |
 |
Summary | 性感染症は、出産時の合併症のリスクや、HIV感染リスクを高めることが判っており、母子の健康、HIV感染予防の観点からも公衆衛生上の優先課題である。罹患者の大半は無症状だが、費用や診療提供体制等に関する理由から、低・中所得国では有症状の患者にのみ治療を行なっているため、無症状患者による感染の増加や、安全な出産への影響が危惧されている。近年、無症状患者の早期発見、早期治療を行うため、感染症の簡易迅速検査(Point of Care Testing: POCT)を導入することが注目されている。 POCTは、高度な設備を必要とせず、短時間で結果が得られるため、患者は身近な保健・医療施設で診断が受けられる。POCTの導入に向けては、POCTをどのように一次医療施設での通常診療に位置づけ、効果的な実用化を図るべきか、診療ガイドラインの策定と体制の強化について議論が続いている。本研究は、マダガスカル、南アフリカ、ジンバブエで、離散選択実験を用い、POCTの利用を促すための要件を、患者の視点から明らかにし、POCTを用いた性感染症の診療ガイドラインの策定に貢献することを目的としている。 |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 国際共同研究加速基金 22KK0143 | HIAS team members | 本田文子 |
 |
Summary | This study aims to evaluate the effectiveness of graphic health warnings (GHWs) and pharmacist-led lifestyle counseling on tobacco cessation and associated health outcomes in Bangladesh and Pakistan. Using a randomized controlled trial (RCT) design involving more than 10,000 smokers, the research will measure the interventions’ impacts on smoking cessation rates, blood pressure control, diabetes management, and quality of life. Findings from this study will provide evidence for low-cost, scalable strategies to strengthen tobacco control and prevent noncommunicable diseases (NCDs) in resource-limited settings. Project [2025-04-01 – 2028-03-31] ※日本語訳準備中 |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 基盤研究(B) 25k0848 | HIAS team members | Miznaur Rahman, Ryota Nakamura, Shamima Akter, Motohiro Sato |
 |
Summary | This study evaluates the effectiveness and cost-efficiency of pharmacist-led interventions to improve hypertension control and medication adherence among 3600 hypertensive adults in Bangladesh, and Pakistan through a cluster randomized controlled trial (cRCT). Forty community pharmacies per country will be randomly assigned to either intervention or control groups. Pharmacists in the intervention group will deliver educational training, lifestyle counseling, phone calls, text messages, and coordinated care. Primary outcomes include blood pressure reduction, while secondary outcomes encompass medication adherence, hospitalizations, lifestyle changes (diet, smoking), improved health knowledge, and cost-effectiveness measured by incremental cost per quality-adjusted life year gained. This pharmacist-driven health promotion model has the potential to significantly reduce morbidity, mortality, and healthcare costs associated with hypertension, enhance pharmacist capacity, and strengthen community-level patient-provider relationships. Project [2022-04-01 – 2025-03-31] ※日本語訳準備中 |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 基盤研究(B) 23K24566 | HIAS team members | Miznaur Rahman, Ryota Nakamura, Motohiro Sato |
 |
Summary | 公的医療における効率的な資源配分は世界的に重要な政策課題である。費用対効果評価はその有効な手段であり、医薬品、医療機器、医療人材の配置等に関して費用対効果評価を活用した予算配分の仕組みを各国が導入している。費用対効果評価の価値は、評価結果を判断するための基準(閾値)が適切に設定されているかに懸かっている。ほぼすべての国において現状運用されている閾値は科学的根拠に乏しい。本研究では、日本、ブータン、シンガポール、タイにおける費用対効果の閾値を行政データ等から定量的に導出し、また閾値を変更した際の医療資源配分への効果を推定する。研究成果の政策インパクトを最大化させるべく、関連する各国政府機関等と連携して研究を進める。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | 中村良太 | |
| Website | https://thesapphire.health/ |
 |
Summary | ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)、つまりすべての人が医療サービスに公平にアクセスできるようにすることは、2015年に国連総会で採択された主要な持続可能な開発目標の1つである。しかし、アフリカのサブサハラ地域(SSA)では、多くの世帯が依然としてケアを求める際に経済的困難を被る高いリスクに直面している。この問題に対処するために、多くの政府は最近、日本を含む国際パートナーからの支援を得て、国民の医療経済的保護を強化することに取り組んでいる。 本研究では、データが古いもしくは、不足している西アフリカ 8 か国(ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、セネガル、そしてトーゴ)を対象とする。地域、国、地方レベルでの壊滅的な医療費の発生率と医療保険料率の最新の推定値を提供することに加えて、現在の公的医療保険制度の改革が国民に及ぼす潜在的な影響についての経済的福祉の側面からの洞察を提供する。SSA の多くの政府が UHC を達成するためにケアへのアクセスにおける不平等を減らすことに取り組んでいる現在、このようなエビデンスは非常に重要である。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Thomas Rouyard、中村良太 |
 |
Summary | 金銭的インセンティブが特定の健康行動、特にワクチン接種や病気のスクリーニングなどの「1回限りの」予防行動を促進する可能性があることを示唆するエビデンスが示されている。低・中所得国からのエビデンスは限られているものの、その有効性に注目が集まっている。 2022年、オックスフォード大学およびガーナ大学との共同研究として、ガーナの農村部で野外実験を実施し、新型コロナウイルス感染症ワクチンの摂取に対する現金奨励金の影響を評価した。 この結果は、少額の現金によるインセンティブの有効性、そしてより重要なエビデンスとして、インセンティブを受け取らなかった近隣の人々へのマイナスの波及効果がないことを実証した。しかし、金銭的インセンティブが被験者内にマイナスの波及効果をもたらすかどうかについては、未解決の疑問が残る。新型コロナウイルスワクチンの接種など、特定の健康行動に対するインセンティブを受け取った個人が、追加のインセンティブを必要とせずに同様の予防的健康行動を行うというその後の決定に影響を与えるかどうかは依然として不明である。既存の文献におけるこのギャップに対処するために、新型コロナウイルス感染症試験で奨励金を受け取った参加者と受け取らなかった参加者の間で結核検査の遵守状況を評価する新しい実験を実施する。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Thomas Rouyard、中村良太 | |
| Website | https://oxford-candour.com/about-us |
 |
Summary | 2 型糖尿病 (T2DM) の負担が増大し、世界中で医療費が上昇しているため、医療システムのコストを最小限に抑えながら、T2DM 患者の持続的な自己管理行動を促進できる介入を特定することが不可欠となっている。本研究の目的は、幅広いプライマリケア設定にわたって簡単に実装および拡張できるように設計された新しい行動変容介入 (フィードバック) の効果を評価することである。 クラスターランダム化比較試験(RCT)は、日常の糖尿病診察中に一般開業医が実施することを目的とした、個別化された複数の要素からなる介入の効果を評価するために実施される。この介入は、医師と患者のパートナーシップを強化して持続的な自己管理を動機付けることを目的とした 5 つのステップで構成されている: (1) 「心臓年齢」ツールを使用した心血管リスクのコミュニケーション、(2) 目標設定、(3) 行動計画、(4)行動収縮、および (5) 行動に関するフィードバック、である。我々は、日本の20のプライマリケア実践からT2DMおよび最適以下の血糖コントロールを有する成人264名を採用し、介入群または対照群のいずれかに無作為に割り当てられることを目指す。主要評価項目は、6 か月の追跡調査における HbA1c レベルの変化である。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Thomas Rouyard、井伊雅子、中村良太、森山美知子 |
 |
Summary | 加工食品、砂糖入り飲料、飽和脂肪酸の大量摂取を特徴とする不健康な食生活は、慢性疾患の一因となっている。本研究は以下の3つを目的とする。1)食生活に関する政策介入の健康アウトカムへの効果について、既存のエビデンスを系統的にレビューする。2)ペアワイズメタアナリシスを用い各政策のプール効果を検証する。3)食生活に関する政策介入の効果の社会経済的公平性を評価する。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Shamima Akter、 Thomas Rouyard、Md. Mizanur Rahman、中村良太 |
 |
Summary | This project provides comprehensive monitoring and reporting on progress toward UHC and inequalities in African countries to support achieving Health for All. It produces a health atlas that helps policymakers identify priorities and reallocate resources properly in future national health programs. |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 特別研究員奨励費 22KJ2761 | HIAS team members | Phuong The Nguyen (PI) |
 |
Summary | This project provides comprehensive monitoring and reporting on progress toward UHC and inequalities in African countries to support achieving Health for All. It produces a health atlas that helps policymakers identify priorities and reallocate resources properly in future national health programs. |
|---|---|---|
| Asahi Glass Foundation | HIAS team members | Phuong The Nguyen (PI) |
 |
Summary | This project provides comprehensive monitoring and reporting on progress toward UHC and inequalities in African countries to support achieving Health for All. It produces a health atlas that helps policymakers identify priorities and reallocate resources properly in future national health programs. |
|---|---|---|
| JSPS 科学研究費 基盤研究(A) 23H00049 | HIAS team members | 佐藤主光、中村良太、Rahman Mizanur、Rouyard Thomas、本田文子、Phuong The Nguyen |
 |
Summary | テクノロジーベースの介入(TBI)は、世界中の子どもたちの定期的なワクチン接種率と適時性を向上させるために広く使用されている。本研究では、ペアワイズメタアナリシスとネットワークメタアナリシスを実行して、各結果に対する介入の直接的および間接的効果とその費用対効果を推定する。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Rashedul Islam |
 |
Summary | 日本やその他の国では、新型コロナウイルス感染症ワクチンを配布するための標準的なアプローチは、各段階で年齢とリスクグループの異なる組み合わせを対象とした多段階の展開を通じて実施される。このような政策の設計を最適化するために、日本でワクチンが展開される前に、まず SEIR モデルを調整してウイルス感染パターンを捕捉する。次に、考えられるすべてのターゲット戦略を調査して、死亡の最小化、症例の最小化、重症者の最小化という 3 つの政策目標に最適な戦略を特定する。本研究の結果、年齢層とリスクグループを混合する方が、個々のグループを個別に標的とするよりも優れた効果を発揮し、ウイルス伝播性が高い状況下では死亡をさらに減らすために、低リスクの若年成人が最高齢の年齢層とともにますます標的となることを示した。高齢者または高リスクのいずれかを対象としたより単純な展開では、有効性の高いワクチンを使用することで、展開における最適ではないターゲットによる健康損失を軽減できることを示した。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Hongming Wang、井深陽子、中村良太 |
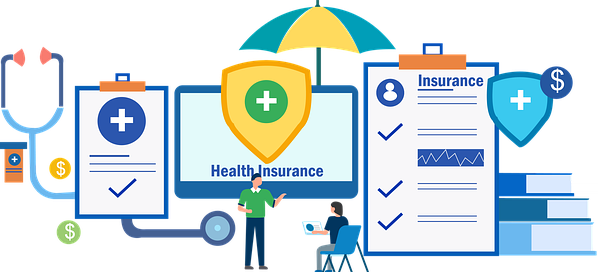 |
Summary | 本研究の目的は、幼少期に国民皆保険に加入することが、壮年期の健康と経済的成果に及ぼす長期的な影響を推定することである。 1956年から1961年にかけて日本で皆保険が段階的に導入されたため、改革前は当初保障率が低かった都道府県で保険適用率がさらに増加し、この政策により改革期間中に生まれたコホート間でエクスポージャーに外生的な変動が生じた。この変動を利用して、現在の人口調査を使用して、死亡率、罹患率、教育および雇用の結果に対する曝露の長期的な影響を推定する。これらの結果は、最近保険適用範囲を改革または拡大している国々の政策議論に示唆を与える可能性がある。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Hongming Wang |
 |
Summary | ここ数十年、平均寿命や障害のない健康寿命などの健康指標は、国民の幸福度の指標としてますます重要視されている。本研究では、20 世紀後半以降の世界中の平均寿命と健康寿命の収束を初めて体系化した。世界各地の輸送コストを大幅に削減した輸送技術の進歩を利用して、グローバル化する世界における貿易拡大が後進開発途上国の死亡率を減少させたかどうか、またどの程度減少したか、その背後にある死亡と疾病負担の具体的な原因を調査する。死亡率への影響、国家の健康プロファイルが経済的説明をどのように補完できるかなど、急速なグローバル化の期間における幸福の増加をより完全に理解することを目指す。 |
|---|---|---|
| HIAS team members | Hongming Wang |